先日、新聞で「トランプコイン」の記事を見かけました。
記事の内容自体は、「トランプ氏が自分の名前の仮想通貨で大金を稼いでいるからそれはどうよ?」みたいな話。正直それはどうでもいいんです。
仮想通貨といえば、ちょっと前に流行った「ビットコイン」しか知らない私。
「トランプコイン」っておもちゃかなんかですか?
で、ちょっと調べてみると、トランプコインをはじめ、ビットコインなどの仮想通貨には「ブロックチェーン」とかいう技術が使われてるらしい。
そしてもう少し調べてみたら、思ったんです。
「もしかしてLGBTQの人たちにとっても希望がある技術かもしれない」
- 結婚していなくても、パートナーと共有口座を持てる
- パートナーシップ制度がない場所でも、関係性を証明できる
かも。。
今回はそんな、ブロックチェーンとの「はじめまして」のお話です。
そもそもブロックチェーンってなに?
さっきから使っている「ブロックチェーン」、みなさん知っていますか?
私は知らなかったので調べてみました。
読んで私なりに消化して一言で言えば、「とても厳重に記録できるジャーナル」という感じなんでしょうか。ちょっと省き過ぎかもしれませんが、技術論ではないので、ご容赦ください。
超文系で55歳の私でもここまでわかりました。
それがわかったところで、実は私、想像がふくらんで「おもしろいかも」と思ったんです。
ブロックチェーン技術が可能にする「証明」の新しいカタチ
ブロックチェーンがとても厳重に記録できるジャーナルだとすると、もしかしたら、それを使えば、色々な記録や証明の代わりになるかも、って思いました。
つまり、書き換えたり、偽造が難しかったりするならば、これまでの紙ベースでの記録よりよっぽど簡単で、紛失もなくて有益なのかもということです。
例えば、
- パートナーシップ証明が簡単で世界中どこへいっても同じものが使える
- 婚姻関係にない事実婚、内縁関係を正確な記録として残せる
などのことに使える可能性があります。
もう少し深堀りします。
制度に依存しない「関係性の証明」
いま、日本では、同性パートナーは婚姻できません。
その代わりに(当事者としては「代わり」ではないのですが)パートナーシップ制度があります。
マリッジフォーオールジャパンによれば、47都道府県中、県全域で制度があるのは33都道府県。制度自体が全くない都道府県は1つもなく、取り組みは進んでいるようです。
でも、これだって制度がない地域だったらそもそもできないし、現状、私たち2人も住んでいる自治体でパートナーシップを結んでいますが、引っ越しして他の自治体へ行くときは、いったん廃止をしてまたその先で登録をし直さなければなりません。
利用していて言うのもなんですが、自治体ごとって。。。
それが現状の限界なのでしょう。
でも、ブロックチェーンなら。
そこに「2人が合意しています」と記録すると、それは改ざんできないから、全国どこでもいつでも通用する「証明」として使えるかもしれません。引っ越し先に制度があるかどうかや時間的余裕をを気にする必要もありません。
そんな証明があれば、
- 病院での面会
- 賃貸契約
- 緊急時の判断
それから、同性パートナーシップに限らないけれど、やっぱりお金の関係は大切ですよね。
つぎは2人のお金について考えてみます。
安全を実現!お金や契約の「共有」
これは、可能性としてはすごいかも。
「一緒につかうお金の口座がほしいね」なんて言っても、現実は多分無理でしょう。
銀行は連名の口座はとても嫌がります。
どうしてでしょう?
多分それは、「誰のものなのか?」がはっきりしないからだと思います。
でも、これもブロックチェーンなら実現できるかも!
共同ウォレットという形で、2人で使えるお財布が持てるんです。
そこでもうひとつ新しい言葉にお付き合いください。
それは「スマートコントラクト」です。
「スマートコントラクト」ってすごい!
「スマートコントラクト」は、文字通り、「賢い契約」。
あらかじめ決めてある通りの条件が成立したら、その条件通りに実行するということを設定できる仕組みのようです。きっと他のこともできると思いますが、今の理解はここまでです。
例えば、
- 2人が同意したときだけ送金される
- Aさんが亡くなったらBさんにデジタル資産が移る
- 毎月共有ウォレットにお金をためていって、目標額がたまったら、決まっている使途だけに出勤できる
- もしものときの資産分配ルールを設定して自動化する
- パートナーシップでの約束事を見える化する
などです。
言ってみれば、自分たちで自分たちのための「お金のあり方」が決められるっていうことなんだなって理解しました。現在の制度的な「家族」や「結婚」の形にとらわれずに、柔軟に自分たちだけの「カゾク」の関係を、デザインできそうだなって考えています。
スマートコントラクトのこれからの発展に期待です。
とはいえ、まだまだ課題も多いです。
これから解説します。
現実の壁~実現のための課題~
とはいえ、それらが実現するのは、もう少し先だと私は思います。
最大の壁は法的効力が足りない現状
ブロックチェーンを利用することで、2人のパートナーシップの関係が安全に、明確に記録できたとします。
だからといって、
- パートナーが倒れた時に、病院のICUに付き添えるかどうか
- 相続時にスマートコントラクトで財産を移転しても、それが法的に有効かどうか
- 意思表示が難しい状態になった時はパートナーに代理権を与えるとスマートコントラクトで記録しても、実際にそうなったときに認められるか
などは、どれも現状は思ったような効果は期待できそうもないです。
- CUに付き添えるかは、病院次第
- スマートコントラクトによる財産移転は、特に相続では否定されそうだし、遺言としての形式も整ってないのでそれもだめそう。
- 意思表示が難しいときの代理権については、現状任意後見制度を利用した方が絶対に安全。
と言えそうですから、現状では別途方策を立てておいた方が賢明だと思いました。
他にも、
- 嘘の情報を登録されたらどうするのか
- 詐欺に使われる可能性は?
- 専門家の知識もまだ追いついていない
などたくさんの課題があります。
でもいま一番大きな壁は、「それが法律上、通用するかどうか」。
だからこそ、技術だけでなく「制度」とのつながり方に興味深々で期待しています。
LGBTQだけじゃない、多様な関係にこそブロックチェーン
特に日本では、「家族」とか「パートナー」というものに関しては、「制度」がとても大切にされています。
もちろん、わたしはそれでいいと思っています。
でも、少しだけ、その「制度」から外れた人たちも「多様性」の存在としてみんなに知られてきたし、その幸せも考えられるようになってきたのではないでしょうか。
例えば、
- 同性パートナー
- 事実婚の男女
- 内縁関係の男女
- 離婚したけれど元夫婦という男女
- どれにもあてはまらないけれど、何等かの関係性があってのAさんとBさん
など、本当にさまざまな類型が想定できそうです。
そのいずれもが、現状の法的枠組みのなかでは「救われている」とは言い難い存在である気がします。
「制度」自体を変えていくのは、それなりに時間がかかり、大変なことです。
でも技術が進歩し、新しい仕組みに法律上の手当が追いつけば、それは新しい「制度」として、これまでのものと並存することができるのではないかと考えています。
今すぐじゃなくても、いつかきっと。
多様性の当事者であるマイノリティが少しでも自分らしく生きられるために、わたしはその進歩に期待したいです。
まとめ
今回は長くなりましたが、ブロックチェーンやスマートコントラクトについてお伝えしました。
ブロックチェーンは、
- 記録が改ざんされにくいジャーナルのようなもの
- 多様な関係の「証明」に活かせる可能性がある
スマートコントラクトは、
- 多様な関係を自由にデザインできるブロックチェーンの要の仕組み
- 今後の進歩や、法的な解釈によっては、これまでの枠組みではカバーできなかった契約関係が柔軟に対処できそうなこと
がわかりました。どれも夢があります。
その一方で、現状はまだまだ克服しなければならない課題はたくさんあります。だから、いますぐブロックチェーンでの証明やスマートコントラクトでの財産移転が実現するとは考えられません。
でももしかしたら、今後必要不可欠なインフラのようにもなるのではないかと思っています。
今回はここまでです。
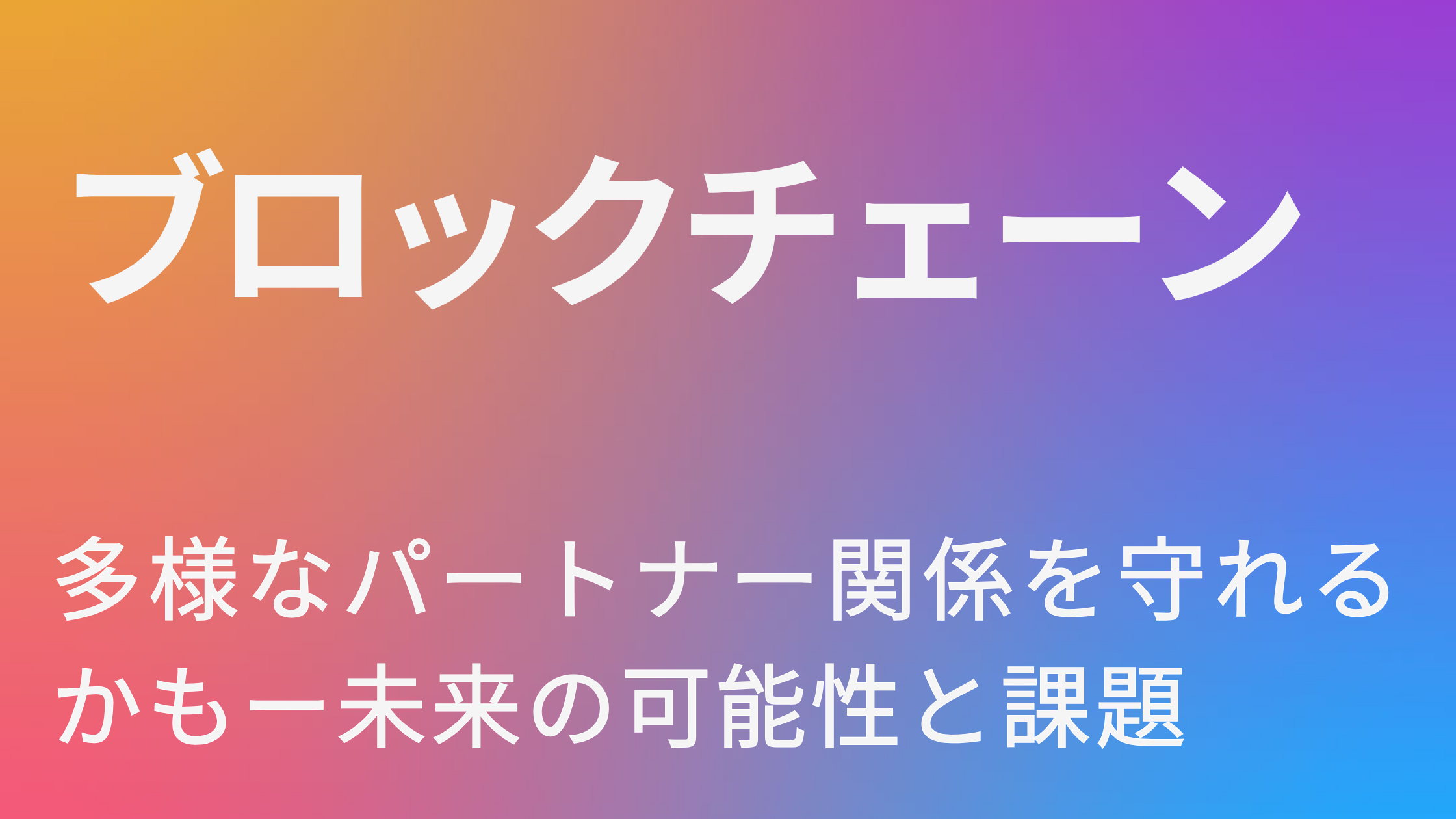



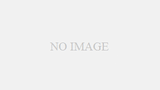
コメント